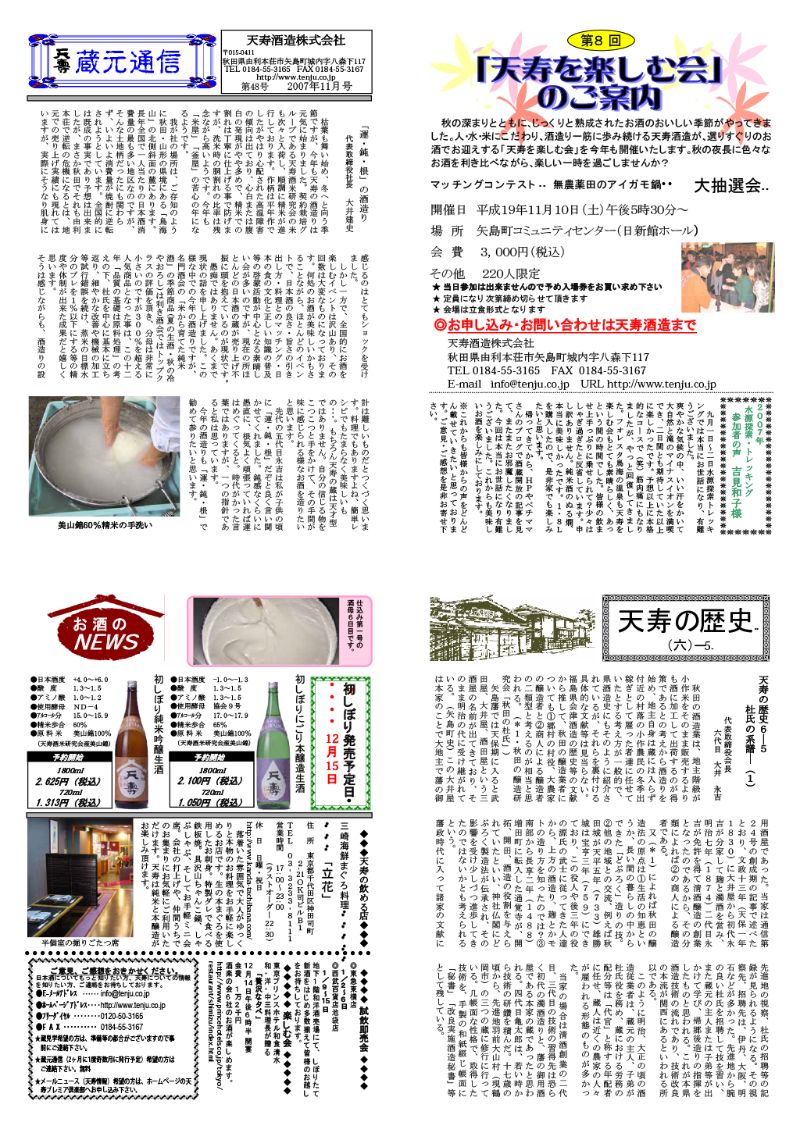人能く道を弘む
代表取締役社長 大井建史
あけましておめでとうございます。
去年の11月に早めの雪が降り始めた割には、たいした積雪も無い穏やかな正月を迎える事が出来ました。天寿の酒蔵では蔵人の新旧入れ替わりや新ローテーションの取り組みの中、順調に酒造りが進み大吟醸の仕込みの準備に気合を入れているところです。
私が入社してから二十年以上過ぎていますが、本当に大きく環境が変わったものだと思います。バブル崩壊後に帰郷した「失われた十年」と言われる期間は、第一次地酒ブームの新人蔵元として特定名称酒の商品開発、地元や名門酒会での販売等の仕事と共にJCや商工会青年部・消防団・祭典の若衆等を夢中でやりながらも、これまでの地盤や地域文化が崩れておらず、地方がここまで地盤沈下するとは予想できませんでした。
しかし、その後細川首相の行なった自由化がボディブローの様に地方の体力を失わせ、地方の文化や行事を無視した祝日の変更や市町村合併により、阪神淡路大震災で叫ばれたコミュニティーを大切にする方向とは真逆の方向に走り続け地方のコミュニティーの崩壊を促進し、無資源国では円安傾向は止めようも無く日本はどんどん貧乏になり、目先の対策しか行なわれない農業は梯子を外された状態で疲弊し続け、近い将来に見える食糧不足の時にはそのつけが跳ね返ってくる事が目に見える様です。
ここ十年の金融再生を中心とした中央経済復興中心の政策の結果、地方の変化は大変厳しいものがあり、人口の減少・財政の悪化は大変深刻な状態になりました。
その様な中、天寿酒米研究会との原料米契約栽培の強化、製造技術向上の為の精米所・醗酵タンク等の設備投資、蒸し米や麹の質向上の為の設備改善、ビン貯蔵のための冷蔵倉庫の建設、花酵母の研究を含む新商品開発、地域の人々と共に進むための各種イベントの開催、小人数体制への移行等弊社も必死に変革の努力を続けてまいりました。
しかし、国内における日本酒の消費量はピーク時の半数を割り、底無し沼のようにその先行きは見えません。ワインブームや第二・第三のビールそしてチューハイ・本格焼酎ブームと酒類業界内の変遷もありました。現在は人口の減少もありますが団塊ジュニア以降のアルコール飲料離れ、飲み会や車よりも携帯電話やインターネット・ゲームなどへ価値観の変化も大きな要因となっております。
何が正しいと言う事は無いと思います。ただ私は日本酒の美味しさをわかって頂きたい。和食の良さ、食べる事の喜び、そこに日本酒がある事の素晴らしさを多くの人と分かち合うために、今年も一生懸命頑張って行きたいと思います。
本年もご愛顧の程、よろしくお願い申し上げます。
天寿の歴史
(六)ー6
杜氏の系譜―(2)
代表取締役会長
六代目 大井 永吉
秋田県が酒質の向上を図るため兵庫県に杜氏推薦を要請し、明治二〇年に来県した鷲尾久八。彼は県内各地で技術指導をしたが、主に矢島地区で醸造法改良の傍ら授業を行い、明治三〇年代に矢島酒の名声を挙げたといわれている。
(秋田の杜氏)
一、真綿 二把
昨秋以来醸酒ノ改良ニ従事スルコト数ヶ月其間佶据勉励為メニ頗ル良結果ヲ呈セリ其功労寡カラス聊カ寸志ヲ表ワシテ之ヲ贈ル
明治二四年四月五日
秋田県羽後由利郡矢島町
矢島酒造組
大井清造
武田吉郎
須貝太郎蔵
大井与四郎
土田安吉
鷲 尾 久 八 殿
これは指導への感謝状であるが、その翌年も矢島に来て酒造技術を指導している。
兵庫県摂津国有馬郡母子村
鷲 尾 久 八 殿
当組合ノ嘱託ニ応シ改良酒醸造ニ従事シ全ク善良ノ功ヲ奏シタルハ当組合ノ甚タ満足スル所ニシテ深ク感謝ニ堪ヘス今般帰県ニ当リ其功ヲ賞シ併テ謝意ヲ表センカ為メ金五円ヲ贈与ス
明治二十五年三月二十五日
秋田県由利郡矢島酒造組合
(以上大井文書)
このように鷲尾の指導に対しその功績に対し深く感謝している。三代目永吉(与四郎)は酒造技術にさらに磨きをかけようと鷲尾久八に長男亀太郎をつけて技術を学ばせ、明治二四年に卒業免状を手にしている。矢島の各蔵元は科学的製造技術が進められた明治末期に先駆け灘の技法を導入実施したのである。
(三―1に前出)
亀太郎は自分の蔵のほか、妻の実家《玉泉》と弟の婿入り先《富士川》も指導しながら手伝い難儀をしている。夜の仕事が多い当時の酒造りで、酒蔵の中に布団を持ち込むほど真剣な人だったと伝えられている。