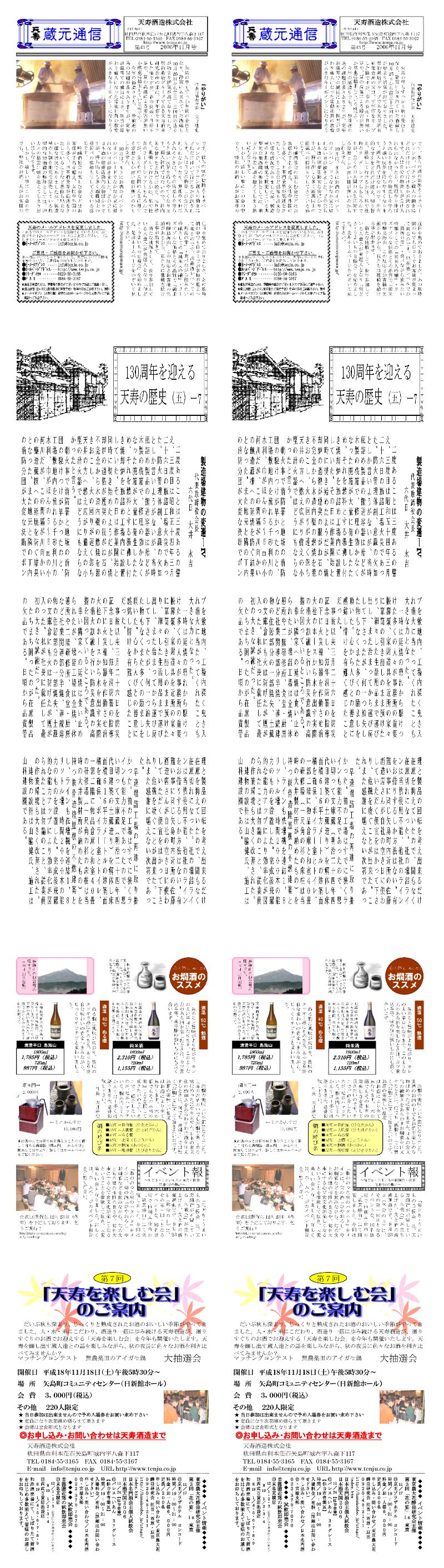新年おめでとうございます
代表取締役社長 大井建史
昨年とは打って変わり、今年の正月は雪も殆んど無く、静かで穏やかな正月を迎えました。昨年中は皆様には大変お世話になり、心より御礼申し上げます。
酒蔵の作業は、暖冬の高温と例年より割れて溶けやすい米ではありますが、その対策も順調に推移しており6日からは出品酒の仕込が始まります。杜氏が見学のお客様に「かえって闘志が湧きます」とお答えしているのを聞いて、苦笑したしだいです。
この酒蔵通信をスタートしたのが 年でしたので、今年で9年目になります。社長になる寸前に所信のつもりで「思い」と言う文章を書き、創刊号の2ページ目に掲載いたしました。また、 年1月「新世紀・新創業の時」を読み返し思いが溢れ、社長になってからのこの8年を振り返り、初心を新たにしなければとしみじみと思う正月となりました。
今更であるのかもしれませんが、毎日のように唱える事によって、沁みてくる言葉と薄れていく言葉があることにも気が付く事が出来ました。
変革とそのスピードの維持を心掛けて参りました。確かに社長になる前の十数年とは比較にならないスピードで変わりましたが、私の非才故に、社会の変化はそれを上回っている事を認めざるを得ません。今の体制が三年前・五年前だったらと私が思ってしまうのですから。自分の尺度が、この間何センチ伸びただろうか、変革の能動者として十分に活動をしただろうかと、青年のように考え込む自分を発見してしまいました。
今年は私も年男、息切れしない範囲で、猪っと猪突猛進してみようと思っております。
今期も12月に農大の研修生を受け入れました。そのレポートに我々の成果とも言える嬉しい事が書かれておりましたので抜粋いたします。
(この蔵は「和醸良酒」という言葉がとても似合う蔵だと思います。
杜氏さんが一人で蔵を引っ張っているのではなく、蔵人さんみんなでお互いを高め合っていて、いつもすごくいい雰囲気です。
この蔵のさらに尊敬するなと思ったことは、蔵人さんの半分以上が酒造検定1級を持っているということです。
みんなが酒造りを熟知しているからいいアイデアがたくさん出ます。
そして出たアイデアをこの蔵はすぐに実行できるところがまたすごいところだと思います。
実行するにはお金もかかるし、機械の改造なんかは逆に壊してしまうというリスクもあるのに、それを許可してくれるこの会社もすばらしいなと思います。
この2週間の実習でこの蔵の発明品をいろいろ教えてもらいましたが、僕が気づけなかった発明品がまだまだある気がします。
また何年たってから来るとさらに進化してそうで楽しみです。 この蔵で実習ができて本当によかったです。)
だから続けていけるのです。気付かせてくれるのは、何時も周りの皆様です。本当にありがたく思います。
今年も精進してまいります。品位を高めてまいります。この蔵人達の心栄えに、今年もご期待ください。
天寿の歴史
(五)ー7
製造場建物の変遷ーⅤ
代表取締役会長
六代目 大井 永吉
壜詰工場火災の時、水利と延焼防止に大きな役割を果たした〝千砂利川〞は市街西北部を貫流し、当社敷地内も横切って流れる小河川で、普段は水量も少なく自然流水の穏やかな川だが、梅雨どきや雪消えのころ大雨が降るとよく洪水を起こし、酒蔵の中にまで水が入りこむことがあった。鳥海山の特殊気象地帯、豪雪地帯である矢島地区は豪雨になることが多く、毎年の降雪量も多い。開発が進むと河川が急速に出水し氾濫するようになるが、当時町の為政者は道路の整備と共に氾濫を繰り返す河川の改修にも力を注いだ。 昭和五十五年〝千砂利川〞の改修が始まった。川巾も広げ川底も舗装し流れをよくする公共工事だが、予想される最大流量に見合う巾と深さを確保しなければならないと言う。そのために当社は川岸ぎりぎりに立つ醸造棟部分の作業場の解体を余儀なくされ、土蔵の入り口前が狭くなって、タンクの出入りが不可能になる設計だった。
幸い昭和四十三年に百石タンクを並べられる貯蔵庫、四十五年には二百石タンクを収納できる貯蔵庫を新築、四十七年には精米所も新築し,すでに仕込蔵も改築してあったので、この際一番古い部分の近代化を図るべく、我が社の歴史を証明する創業時(明治七年)建築の一号蔵は残し、思いきって他の二つの土蔵は解体、木造作業場は移築することを決断、新たに一部二階、鉄骨造陸屋根の製品庫、連結して酒母室、原料処理場の建設に踏み切った。ところが一号蔵が工事中に段差のところから土台が崩れ、その影響で梁も大きくずれて壁も落ちてしまったので、止む無く入り口の観音開きと土戸、格子戸を残こすのみで本体は新しい材料での改築となった。
百年の歴史と伝統を感じさせる建物は住宅部分を除いて殆ど消失してしまうことは実に残念なことであった。人びとはそれを発展の証だと言うが、敷地に余裕があればそれを活かしながら新しい建物に調和さることも出来たと思うが、ぎりぎりの状態では如何ともし難かったのである。 天寿の歴史では未だかつてない大規模な新改築、それに伴う多額の投資であったが、完成後は一日の仕込み量も大きく、作業効率も数段良くなり酒質の向上にもつながり、またコストダウンにも大きく貢献したのである。
その後六十三年に低温貯蔵庫改築、平成一年上槽場改築、平成九年自動製麹棟新築、同十三年独立冷蔵倉庫新築と設備の充実を重ね現在の状態に至っている。改修後の〝千砂利川〞の洪水は一度も起きていない。