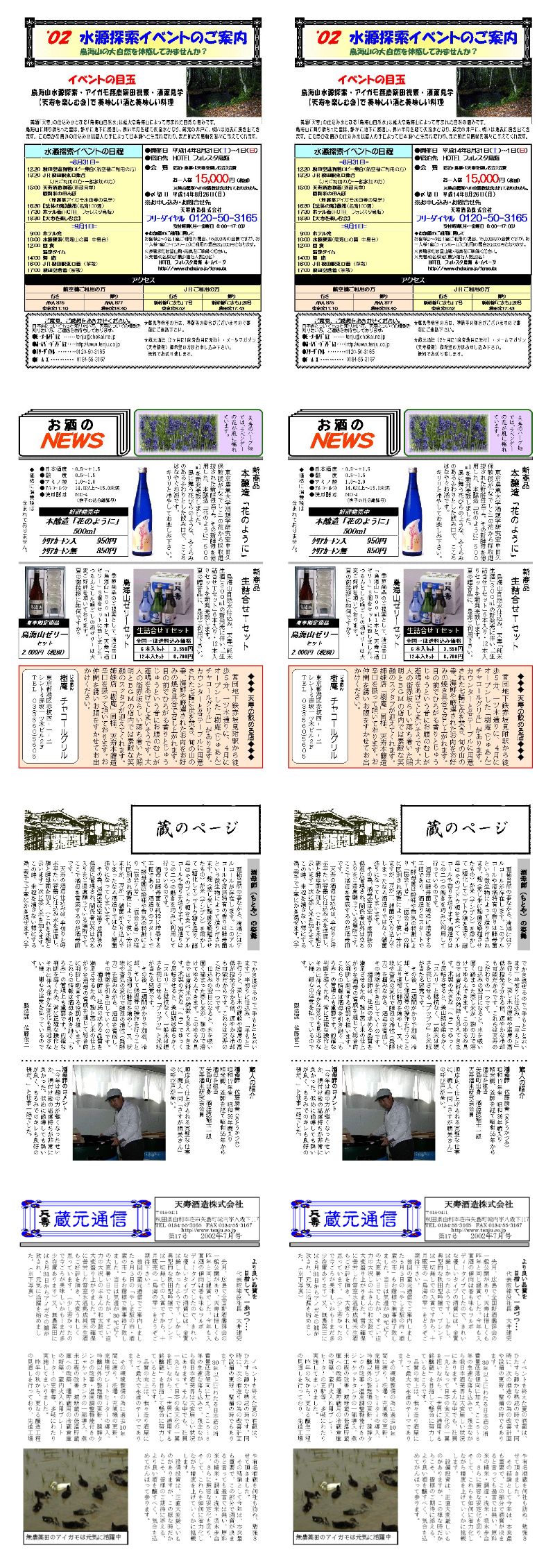今、桜が満開です
代表取締役社長 大井建史
2月15日の酒蔵開放には、お陰様で一,二〇〇名を超える方々にご参加いただきました。本当にありがとうございました。
少しづつではありますが、新企画や改善を行っているつもりですが、如何でしたでしょうか。中には「もっとジックリ酒造りを見てみたい・やってみたい」「一部の体験だけではなく、全工程の体験をしてみたい」などのご意見もあるようです。天寿だけの企画では人数を集める事が難しいですが、熱いご要望があるのでしたら、三十人位の「じっくり酒蔵見学・きき酒懇親会付」とか「酒仕込みを自分たちで行って飲む会」などできるのですが…。(そうすると二十人集まれば一人一・八リットルで約40本?ちょっと多いかな?でも、しぼりたて・夏の生酒・ひやおろし・冬の熟成酒というように、一本の仕込みで四つの味を楽しめるかと…。)
甑倒し
今年は3月14日が甑倒し(米の蒸しが終わり仕込みの終了を指す)です。弊社にとって129回目、佐藤新杜氏にとっては初めての仕込みが終わります。本当に色々有りました。色々やりました。しかし、結果は皆様に飲んで頂いた時に初めて出てきます。皆様の声を受け、検討し、次の酒造りに向かうのです。ですから今は、天寿新時代の始まりでしかありません。これから造り上げて行くのです。
天寿では「感動を持って味わって頂ける酒造り」を目指しておりますが、それは、どんな酒でしょう?世界中からアルコール飲料が雪崩れ込んでおり、ワインブームがあり、焼酎ブームがあり、その多様な嗜好品の中で飲まれる量が激減している清酒の中、天寿を好みとして飲んで頂けるには?経済状況が悪化し、低価格な物にどんどん流れていく中で、世界で一番高価な米を使用して醸す清酒、その中で天寿を指名して頂く為には?
深い混沌の中でもみくしゃになりながらも、思いを実現するためには、「原点に立つ」事しかありませんでした。蔵での造りの見直しも全て「原点・基本」の忠実な実現です。今売れている酒質を真似ても意味は無く、雑誌で珍重がられる家族で造る500石の蔵になることも出来ません。しかし、造りの一本一本を精米歩合とは関係なく、芸術品のように心血を注いでいく事は出来ます。
「原点」とは本当に厳しいものだと思います。目指して初めてその厳しい現実にぶつかります。目指して初めてその高さに気が付きます。結果は全て酒に現れるものだと実感します。造る者の「姿勢」と「思い」がそのまま現れるのです。(恐ろしい事に…
今年の酒が今の天寿です。まだまだ努力が足りないとは思いますが、「思い」は沢山つまっています。
一人でも多くの方にお楽しみ頂ければ幸いです。
蔵のページ
天寿気質
杜氏 佐藤俊二
「ええ酒(良い酒)造りたい」。毎年造り前に思っていますが、杜氏一年目の今年は尚一層その思いが強く、又、責任の重さに緊張感を持って臨みました。
酒造りは、精米、釜、麹、酒母、もろみ、槽(ふね)全ての工程で最善を尽くします。
蔵人は職人(プロ)ですから良いものを目指せば目指す程、どの様に最善を尽くすかを真剣に考えます。その為、酒種毎の何をどの様に向上させるのか?明確な目標を提示し、各担当が理解した上で一丸となって取り組むことが重要です。曖昧な指示など出来ませんでした。
一般的に、仕事にこだわりがあると自分の職責にのみ固執する場合が有りますが、「天寿」の蔵には柔軟性が有ります。
酒造りの一日に各工程の仕事の繁閑は存在します。その時、蔵の中では互いに時間を融通し他工程へ出かけます。そこで気づいたことや行き詰まった事など、職責を超えて気軽に話し合える雰囲気があるのです。
今年、秋田県立大生二名がインターンシップ研修で蔵を訪れ、一週間寝食を共にしました。吟醸酒の搾りを含め、普段通りの仕事をいつものように行い、彼らの希望もあって特別扱いは一切有りませんでした。実習の感想文に「各工程で香りを嗅いだり手で触ったり直接ふれることで勉強になった(中略)本当にチームワークの良い蔵だと思った。その良さが酒に表現されていると思う。改めて人間関係の大切さを実感させられた(後略)」とあり、最大級の褒め言葉を頂いた感がありました。学生に仕事を教えた蔵人共々喜びを分かち合いました。
この様に天寿の蔵人は単に働きに来るのではなく、皆でええ酒を造り、互いに教え合うという気構えを伝統的に持っています。これは天寿の杜氏代々の賜です。私も蔵人と同じ仕事をし、天寿気質を身に付けてきました。
間もなく造りも終盤です。出来上がった酒が「天寿」の蔵を想像させる「ええ酒」であることを願ってやみません。
社員の紹介
総務課
佐藤 玲子(さとう れいこ)
昭和?年十月九日生れ
天寿の窓口である総務課の大ベテランです。女性陣のリーダーとして、チーフを務める、んめものや・イベント等に先頭に立ってアイデアの捻出に余念がない。いつも明るく若々しい声で応対しています。天寿にお電話頂いた方はきっと話をしていらっしゃると思います。
玲子の独り言
まだまだ若い?人達には負けてられないわ!。
お客様が「何をお求めか」「どうしたら一番喜んでいただけるか」を考えて頑張れば、厳しい時代ではありますがきっと女神が微笑んでくれると思っています。お電話をお待ちしております。