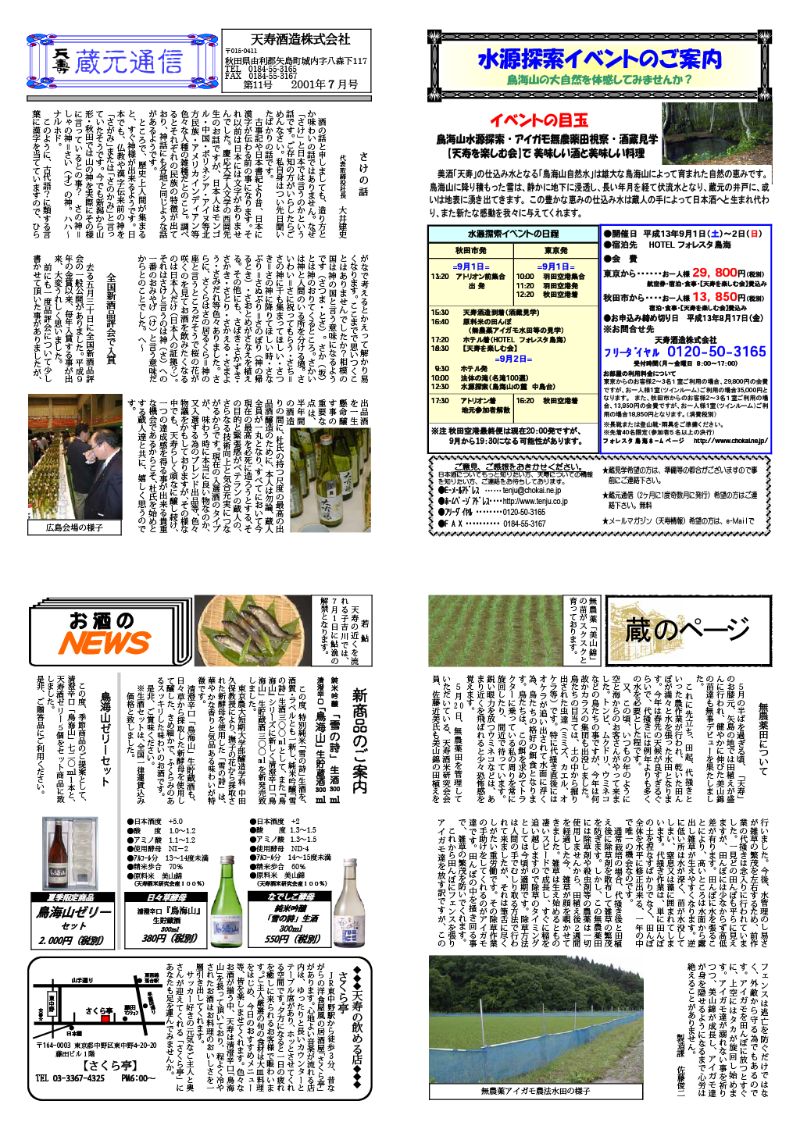128回目の酒造りが始まりました
代表取締役社長 大井建史
秋の味覚本番の季節になりました。日本酒の美味しい季節です。秋田でも、稲刈りが終わり新米が食べられるようになり、秋の恵みによる様々な野菜や果物、そして山の幸・海の幸。あふれんばかりです。
世間のニュースは、暗い話ばかりで心が沈みがちですが、くよくよしても始まらない。こんなときは家族や友達みんなと一緒に、美味しいものを楽しみましょう。
お酒も、暑い夏を越えしっかりと熟成されて、今が飲み頃になりました。ピカピカの秋刀魚を焼いて、なめこや舞茸の酒蒸しにおろしをのせて、純米の燗酒を一杯。心やすらぐ瞬間です。
お酒をおいしく飲むには?とよく聞かれます。ポイントをまとめてお話させて頂きます。
●品質管理の良いお店で
日の当たる所にお酒を置いている様なお店は、お酒の知識が無いところです。常温でも三ヶ月位は品質変化が小さいですし、冷蔵庫に入っているところはそれ以上でも大丈夫です。日本酒は生酒を除いて、開栓せずに冷暗所にある限り、熟成は進みますが悪くはなりません。(お好みの酒質に成るかどうかは別ですが)
●飲む時の温度は
たとえば、大吟醸を飲むときに温度で味比べをされた事はありますか?10度・15度・20度と味わいがぜんぜん異なる事に気が付きます。一つのお酒で三倍楽しむ事が出来ます。お燗も同じ。人肌の40度・50度・60度は熱すぎませんか?外での熱燗の温度に慣らされてはいませんか?昔はお燗番として人ひとりを専門に置いたほど重要な事なのです。
●おいしく飲む為の酒器
昨年の七月号で、ワイングラスのリーデル社で大吟醸グラスを造った話をさせていただきましたが、吟醸などの香りのあるものは、ワイングラスが結構合います。(酸の少ない白ワイン用が良い)その他のお酒も、ぐい呑み型・朝顔型等色々ありますが、値段や素材よりも形と薄さが大きく影響するのです。味にうるさい人に薄い杯と厚い杯に同じお酒を入れて、いたずらしてみて下さい。必ず「薄いほうが断然美味しい」と言うはずです。
●吟醸・純米は燗してはいけない?
そんな事はありません。確かに香りの高い吟醸は燗には向きませんが、香りの少ない古酒系のものはぬる燗の良く合う物があります。純米・本醸造はお燗の合わないものの方が少ないのです。その発見が美味しさと楽しさをひろげてくれます。
天寿酒米研究会の米の出来は順調でした。(無農薬の10a当たりの収量は5.5俵と悪かったが)10月22日には蔵人もそろい、眠っていた蔵に活気が戻りました。今年も張り切って酒造りに励みます。12月の中旬にはしぼりたて生酒も出荷出来る予定です。ご期待ください。
蔵のページ
10月11日、蔵に新米の美山錦が入庫しました。いよいよ今年の酒造りが始まります。
今年の美山錦の作柄は上々です。極端な干ばつ、低温等の変動要因がありませんでしたし、台風の影響も受けませんでした。(前号でのお祈りが通じた為?)只、全般的に気温が高めに推移した為か、収穫期が平年より1週間程早まった感があります。「地球温暖化」と云う言葉が思い浮かびますが、自然を相手にしているだけに説得力があります。
原料米が順調であるとつい油断をしがちですが、この様な年ほど身を引き締めながら酒造りに向かわなければなりません。何故ならば、酒造りの技そのものが酒質に現れる年となるからです。とりわけ昨年以上の酒質を目指す為、課題は山積となります。例えば、香り高く華やかな酒をより澄んだ形にするには?。丸くなめらかな質を求める酒に、よりふくらみを持たせるには?。又その両方を重ね持つ酒には、さらに後味の余韻を付加する為にはどうするのか?。これら思い当たる点に一つずつ工夫を加え、向上を目指していくのです。
天寿では「酒造りは米作りから」を理念として酒造りを行っています。私も他人まかせの米作りではなく、自ら米作りに関わって「天寿酒米研究会」の一員となっています。栽培過程が明らかな良質原料米の安定供給が酒質向上の大前提であると考えます。
そして大切なことは、これら私共の行動をお客様へお伝えし、共感される内容でなければならないと言うことです。その為一年を通じて酒蔵見学を受け入れています。冬は酒造りを、夏は酒蔵と田んぼとをです。
今年の秋、田んぼにお客様がお見えになりました。歓声をあげながらの稲刈りを通じて、手にした稲穂の一粒ひとつぶから天寿の酒が生まれることを体験していただきました。※写真上
今年はこの米を使用して仕込むものを含め、109本の仕込みを行います。
その1本1本に工夫と情熱を込めて醸します。新酒の仕上がりを楽しみにお待ち下さい。
製造課係長 佐藤俊二
蔵人の紹介
頭(かしら)高橋重美(たかはししげみ)
昭和19年生 昭和38年入蔵以来麹造りを専任。麹の品質に徹底的にこだわる典型的職人肌。既成概念に囚れず、常に製麹方法の向上を目指す。酒造技能士一級 山内村出身。
疑問に思った事は納得するまで没頭する。以前、機械からの軽微な感電を経験し電気回路に興味を持った。この時以来電気トラブルにはテスターを片手に原因を探し出す特技を持つ。自作で麹品温監視機まで作製する。息子さんの名は「幸司」(こうじ)。こだわりの人である。
頭のコメント
新しい手法は取り入れながらも、伝統のある天寿の味を変えることなく酒造りを続けていきたい。