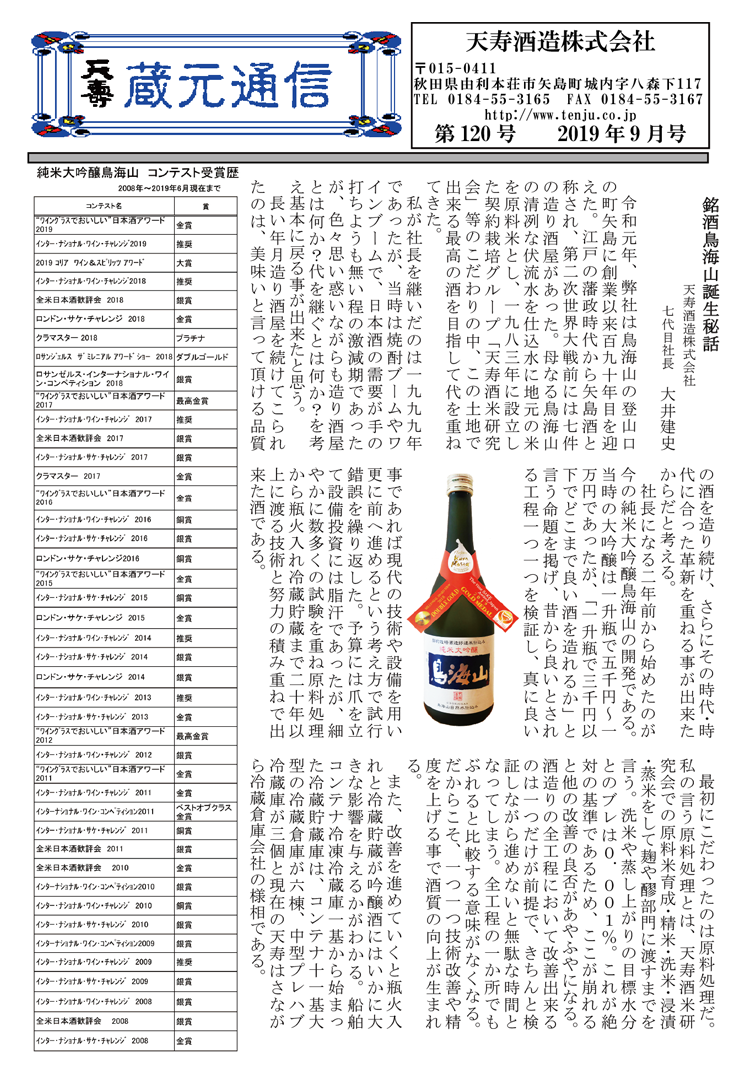謹賀新年
代表取締役社長 大井建史
明けましておめでとうございます。旧年中は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
昨年は震災や台風などで、大変な被害がもたらされました。被災された沢山の方々に心からお見舞い申し上げますと共に、一日も早い復興をお祈りいたします。
いよいよオリンピックイヤーとなりました。日本国中その期待に盛り上がっておりますが、皆様如何お過ごしでしょうか?
私は還暦となり社長就任20年目となりました。地元では「還暦祝い」と称し、厄払いの後中学校単位でお祝いの宴を行うのですが、久しぶりに会う友は当然のことながら皆しっかりと年を重ね、来し方や定年・その延長の話をしながら、気分だけは若いころに戻って楽しみました。年の取り方にも個人差がしっかり出るものなのですね。
そのような中、天皇陛下がご即位され「令和」と元号が改められました。伝統儀式を目にすることが出来、あらためて日本文化の豊かさや美しさを感じられました。
ここで出すのは不敬ではありますが、我々は天皇陛下と同じ学年であり、これから新天皇としての職務に臨まれる覚悟あるお姿に、勇気と気合をいただきました。
10月から190年目の酒造りが、蔵の中で気合を込めて続いております。今年の秋田の酒米は、出穂した8月2日前後からお盆過ぎまで35度を超える猛暑日が続き、それまで日照不足で一週間ほど遅れているとされていた稲の生育も、お盆過ぎには一週間例年より進んでいる状態でした。結果収穫量は104%と良好でしたが重度の高温障害が発生し、一本目の仕込みは粕歩合が50%近く、大吟醸の出品酒並みの酒化率となる程で、原価の高いお酒に成りました。
非常に溶け辛い米質で製造方法を練る必要があります。昨今の異常気象でこの様な対応を何度か迫られ経験も有りますが、これを如何に早く適した形に出来るかが腕の見せ所。
最初に搾られたお酒の状況を検討して、想定との差異が大きい程大胆な調整が必要になります。
蒸米や醸造温度等で調整して行く事になりますが、県内産でも品種や産地・生産者により品質のばらつきが有り、何れにしましても味ブレの出やすい年になりそうです。
弊社杜氏の一関陽介は37歳。まだまだ最年少に近い杜氏ですが今年8造り目と中堅と言ってよい回数となってまいりました。杜氏はもとより蔵人全員で精進しておりますので、天寿190造目の本年もよろしくお願い申し上げます。
飲みニケーション
杜氏 一関 陽介
あけましておめでとうございます。本年も宜しくお付き合いください。
さて、令和最初の酒造りも序盤を過ぎ、蔵はまもなく年に一度の鑑評会出品酒の仕込みが始まろうとしています。昨年の暮れからは有難い事に沢山のご注文をいただき、普段酒造りをしている蔵人メンバーも総出でラベル貼り・包装等出荷作業に勤しみました。例年の十二月であれば、気温も下がり酒造りにはベストな時期に入っているわけですから仕込みに精を出している時期なのですが、「飲んで頂くところまでが酒造り」と頭を切り替え、12月の仕込みを例年より少なくし、人手不足の出荷作業に重点をおきました。そんな想いと共に、皆様に本年度の新酒も美味しく召し上がっていただけていればと切に願うばかりです。
日頃から沢山の方に様々な場面で飲んでもらいたいと思いながら酒造りをしている私ですが、暮れに「忘年会スルー」という言葉を耳にして、少し思うことがありました。
忘年会をスルーしたい理由としてSNS等で良く見かけるのは、「無意味」・「時間がもったいない」・「仲の良い人だけなら良い」・「お金と時間を費やしてまで上司の話を聞きたくない」・「幹事が嫌だ」とか。年齢や立場によっても理由は様々あるようですが・・・。昔流行った「飲みニケーション」という言葉を聞くことも最近は無くなり、内容自体が否定されがちであることが私は非常に残念でなりません。
今やSNS等では沢山の人と簡単に繋がる事ができる等、様々なコミュニティが存在する時代になりました。実際に面と向かって酒を酌み交わしたり、会話をすることが少なくなりつつある今だからこそ、自分の身の回りにいる人の考えを知る事、人のありがたさに触れることが出来る場を作ることが大事だと考えています。そこで笑顔が生まれれば、明日もまた頑張ろうと思う活力が湧き、モチベーションが上がるのではないでしょうか。そんな質の良い意味のある飲みニケーションは必要です。その為には皆が「是非参加したい」と思えるような、スルーしたら後悔する空気を作っていくことが前提だとも思います。
最後に、チームで一つの物を造る私たち蔵人の仕事も、皆が同じ方向を向くことが大切です。一致団結と知識・技術の向上を目的により良い飲みニケーションを図り、昨年よりも更に良い酒を目指します。ご期待ください。
本年も宜しくお願い致します。